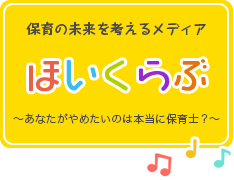- みんなが保育士を辞めたい理由を聞いてみました
- 戻る
- みんなが保育士を辞めたい理由を聞いてみました_TOP
- 保育士として長く働き続けるなら
- 保育士を辞めて後悔したケース
- 保育士を辞めて良かったケース
- 保育補助の仕事を辞めたい
- 保育士になって1ヶ月…もう辞めたい
- 保育士に向いてないから辞めたい
- 保育士の職業病 膀胱炎
- 保育士の職業病 腱鞘炎
- 主任保育士が辞めたいと思う理由
- 新人指導が大変で保育士をやめたい
- 腰痛がひどくて保育士をやめたい
- 音痴が恥ずかしくて保育士をやめたい
- うつ病で保育士をやめたい
- パート勤務の保育士をやめたい
- 保育士の通勤事情
- 制作が苦手で保育士をやめたい
- 加配保育士がきつくてやめたい
- 年度途中で保育士を辞めたい
- 子どもの怪我によるトラブル
- 保護者からのクレームで保育士をやめたい
- 夏休みがなくて保育士をやめたい
- 仕事ができなくて保育士やめたい
- 給料が安い
- 保育士の仕事がとにかく辛いからもう辞めたい
- 人間関係が悪い
- 有休も育休も産休も休めない
- 子どもが多すぎて全体を見れない
- 持ち帰り仕事や残業が多い
- 新卒にも保育士を辞めたい理由を聞いてみました
- 保育士1年目でやめたい
- 保育士2年目でやめたい
- 保育士3年目でやめたい
- 保育観が合わない
- 保育士4年目にやめたい
- 保育士5年目でやめたい
- 保育士6年目でやめたい
- 保育士7年目でやめたい
- 保育士8年目でやめたい
- 保育士9年目でやめたい
- 保育士10年目でやめたい
- 保育士に聞く・福利厚生や待遇のホンネ
- 保育士の転職に必要な基礎知識
- 事業所内保育所はどんな保育所?
- 保育士の資格・経験を活かせるお仕事
- 戻る
- 保育士の資格・経験を活かせるお仕事_TOP
- 保育士から認定こども園への転職
- 保育士から病児保育園への転職
- 保育士から保育ママへの転職
- 保育士からインターナショナルプリスクールへ転職するには?
- 保育士から児童福祉施設(施設保育士)へ転職に何が必要?仕事内容や必要な資格についてチェックしよう
- 保育士から企業内保育施設への転職で必要な資格はある?仕事内容や大変なポイントも解説
- 保育士から居宅訪問型保育への転職に必要な知識や資格は?居宅訪問型保育の特徴も詳しく解説
- 保育士から放課後デイサービスへの転職をするときに必要となる資格は?
- 保育士から託児所へ転職するには?
保育園との違いや大変なポイントも紹介 - 保育士から介護士への転職はできる?
介護福祉士の資格取得は? - 保育士から学童保育士へ転職するには?学童保育士の仕事内容と資格
- 保育士からベビーシッターへの転職に何が必要?仕事内容や苦労も知っておこう!
- ほいくらぶについて
人間関係が悪い
どの職種や業種でも、人間関係に悩む方は多いと思います。特に保育士の仕事は女性が多い職場なので特有の問題があったり、スタッフだけでなく親との人間関係にも気を遣う必要が。保育士は人間関係においてどのような悩みを抱えているのか、ほいくらぶは独自の調査で100名の保育士に意見を伺いました。(※独自アンケート期間2019/4/15~2019/4/30)
人間関係を理由に保育士を辞めたい人は47.2%
人間関係に疲れ、保育士を辞めたいと回答した保育士は、47.2%となりました。(※複数回答の結果)
保育士の仕事は、同僚や上司、さらには保護者など、狭い空間の中で複数の人間関係に気を使います。トラブルへの対応ひとつ、声のかけ方ひとつで問題になることもあるでしょう。私たちが思う以上に、気苦労の絶えない仕事だからこそ、職場の人間関係は穏やかで気楽であってほしいですよね。
人間関係が辛い理由「他の保育士に馴染めない」
同僚である他の保育士と打ち解けられない、馴染めない…就職したばかりの新人保育士には、とくにありがちな悩みです。気まずいムードでストレスが溜まるのはもちろんのこと、保育に関する情報共有にも支障をきたしてしまうことも。「自分から積極的に話しかける」など、打ち解けるための努力で改善することもありますが、馴染めない原因が業務の量や職員同士の派閥にある場合は、退職を検討せざるを得ないこともあります。
人間関係が辛い理由「仕事を任せてもらえない」
「ミスが多いから」といった理由で、やりがいのある仕事を割り振って貰えないケースです。このような状況が続くと職場に居づらくなるばかりか、保育士としての自信までなくしてしまうこともあるでしょう。
ミスを防ぐ工夫や仕事への慣れにより信頼と自信を回復できることもありますが、相手が明らかな悪意を抱いている場合、関係の修復は難しいかも知れません。
人間関係が辛い理由「正規職員とパート保育士の軋轢」
園によっては、正規職員とパートの保育士との間に壁があり、互いにいがみ合うような状態になっていることもあります。正規職員はパート保育士に対して「責任感が足りない」「役割分担がアンフェアでずるい」、パート保育士は正規職員に対して「業務内容が同じなのに賃金に差があるのはおかしい」といったモヤモヤを抱くことが多い模様です。不満が高じて関係がこじれてしまうと、職員同士の対立や職場いじめといった大きなトラブルにつながることも。
人間関係が辛い理由「上司の横暴」
園長や副園長が威圧的であったり、現場で働く保育士たちの意見を軽視したりするケースです。中には「園長が指定する本や物品を自腹で購入しなければならない」など、不可解な独自ルールを押し付けられて困っているという保育士も。園のトップである園長とのトラブルの場合、努力や話し合いで解決できる望みも薄いことから、退職や転職という結論を出す人も少なくありません。
人間関係が辛い理由「派閥争いがある」
同じ園に勤める保育士同士であるにも関わらず、スタッフが2つの派閥に別れていがみ合っている…残念ながら、このような構図は珍しくありません。派閥争いを経験した保育士からは「どちらの派閥につくか選ぶよう迫られた」「ことある事に陰口を聞かされ、気が休まらなかった」といった悲痛な声も。「新人保育士が対立する派閥に属している場合、わざと業務を教えない」など、保育の質にまで影を落とすような深刻なケースもあります。
人間関係が辛い理由「保育方針が合わない」
他の保育士や園長などの上司と、保育方針の食い違いが発生するケースです。保育士同士の場合は、冷静に話し合ったり、自分の視点を見直してみたりすることで、意見のすり合わせを図ることもできるでしょう。しかし、相手が園長である場合は、諦めて合わせるか園そのものを退職するかのどちらかしか選択肢がないことも。
人間関係が辛い理由「職場いじめがある」
職場内の特定の人物に対して無視をする、根も葉もない噂を流すといった、いわゆる「職場いじめ」。本来ならば決してあってはならないことですが、残念ながら保育の現場でも起きてしまうことがあります。
いじめ行為の証拠を集め、上司や然るべき機関に相談して解決を図るという方法もありますが、まずは何よりも自分の心身を守ることが先決。早期の解決が見込めない場合は、職場を離れるのも手です。
人間関係が辛い理由「モンスターペアレントがいる」
保護者との人間関係も、保育士を悩ませる要素のひとつ。とくに頭が痛いのが、理不尽な要求ばかりを突きつけるモンスターペアレントです。「丁寧に話を聞き、共感を示してあげる」「お互いに理解し合えるよう、日頃からコミュニケーションに努める」といった工夫で事態の改善を目指すこともできなくはありませんが、そんな余力もないほど疲弊しているという人も少なくないでしょう。
人間関係が辛い理由「パワハラが横行」
園長や主任といった上司からのパワハラに苦しみ、退職を考えるほど追い詰められる保育士もいます。暴力をふるう、怒鳴る、罵るといった行為はもちろん、「明らかに不可能な量の仕事を押し付ける」「わざと仕事を与えない」「人間関係から疎外する」などもパワハラに該当します。過去には、「理事長のパワハラに耐えかね、園の半数以上の保育士が一斉退職する」「保育士への暴力行為が露呈し、副園長が逮捕される」など、非常に深刻な事例が発生した園も。
人間関係が辛い理由「先輩・後輩との関係が悪い」
保育士は、子どもたちの命を預かる仕事。その緊張感から「先輩に辛く当たられる」「新人指導がうまくいかない」といった先輩・後輩間のトラブルも生じやすいのが現状です。改善のポイントは、日頃から積極的にコミュニケーションを取って信頼関係を築くこと。しかし、人間関係がもつれる原因が過多業務などにある場合は、職場そのものを変えたほうが良いこともあります。
職場の人間関係で悩むトラブルの対象
園長/施設長
園長や施設長といった人物は責任者であり、基本的に園内のトラブルを解決したり悩んでいる保育士からの相談に乗ったりすべき立場です。しかし、実際は下の立場にいる人間に対して一方的に考えや不満を押しつけてくるケースもあります。
主任
主任は園長などよりも保育士に近い立場の責任者ですが、だからこそ日常的に接する機会も多く、主任とのトラブルはむしろ園長とのトラブルより大きなストレスの原因になる例もあります。
同僚
一緒に働く同僚といっても、先輩後輩といった上下関係があったり、同期であっても考え方に違いがあったりと、その関係性は様々です。そのため、心強い味方になってくれる場合があれば、逆に同僚から嫉妬されたり、他の人間関係のいざこざに巻き込まれてしまったりといった恐れもあります。
経営層/本部
大きな保育園などであれば、園長の上にオーナーや本部の人間がいることもあります。普段は現場に現れない人間だからこそ、保育士の苦労や努力を知らず、一方的に要求を突きつけてくることもあるでしょう。
保護者
問題のある保護者とのトラブルは、多くの保育士や関係者にとって大きな悩みの種です。また、面倒な保護者とのトラブルを回避するため、園長や経営層などが保育士へ無理難題を押しつけてくるケースもあり、直接的に保護者とのトラブルがなくとも、園内の人間関係を悪化させる原因になることがあります。
人間関係が悪化したエピソード
保育士として働いていて、人間関係が悪化したと感じた瞬間について伺ってみました。

こちらから挨拶をしても無視されたり、話し出すときからケンカ腰の言い方なので、聞いているだけでも怖かったです。

偉い立場の人がいないため(副園長がいないうえ、園長も不在がち)、中堅の保育士がやりたい放題で、仕事も自分たちがやりやすいようにやっていたところが、人間関係が悪いと感じました。

同じような失敗をしたとしても、軽く注意される人と厳しく叱責される人がいました。

妊婦に対して嫌な対応をする人がいて、そういった不満を上司に相談して改善を求めても何も対応してくれなかった。
あくまでアンケート結果の範囲内ですが、仕事のできる人がいばりちらしたり、上司がワンマンであったりと、お互いを支え合い助け合う環境が整っていないように感じます。女性が多い職場のため、特有の悩みを抱える意見も目立ちました。
保育士は、約9割が女性の世界※。すべて保育士が平等にライフイベントを楽しめる環境であってほしいですね。
※参照元:保育士等に関する関係資料(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf)
人間関係を改善するには何が必要?
原因に目を向けて的確な相談相手に話しましょう
人間関係が悪化する原因を考えるにあたって、園全体に問題があるのか、個人的な問題なのかを把握することが大切。個人的な問題といっても、自分に責任があると責めてはいけません。冷静に、相手と自分との関係における行き違いや考え方の違いなどによって起こっているのか、働き方や労働環境によって起こっているのかを認識しましょう。
相談できる相手がいれば、相談するべき。相談相手は、たとえば主任や園長など、解決できる可能性のある人にしましょう。ただ単に周りに愚痴ってしまうと、陰口だと認識されてしまうリスクがありますので、注意が必要です。上司による嫌がらせなど、なかなか相談相手がいない状況であれば、転職や異動を検討することもひとつの解決策ではないでしょうか。
具体的な改善策は?
良い人間関係を築くためには、挨拶をきちんとすることや笑顔で過ごすこと、話を聞く姿勢に気を付けることなどが大切。苦手な相手に最初から拒否反応を示すのではなく、うまく受け流すことを覚えることもときには必要です。相手に尊敬の気持ちをもって、丁寧かつ謙虚な姿勢を見せ、積極的に質問するなど前向きな態度を示しましょう。
陰口や悪口の好きな同僚がいれば、反論をせず、しかし同調もせず、ひたすら聞き役に徹します。「そうだよね」ではなく、「そうなの?」や「初めて知った」など、知らなかったことを今聞いたという立場を崩さず、相手が満足するまで聞いてあげましょう。そのうえで、関わりを減らすべきか、それとも職場を変えるべきかは早急に判断するのが吉。
保育士としてのスキルアップを目指す
真面目に働いていてもトラブルになってしまうことはありますが、保育士としてきちんと仕事ができなければ、さらに問題が悪化するリスクが高まります。特に、保護者との問題では、仕事上のミスなどをきっかけにクレームが激化することもあり、まずは保育士としての仕事を全うすることが必要です。
派閥争いやイジメに加担しない
自分以外の誰かが攻撃の対象になっていた時、その攻撃に加担してしまえば、実は周囲から自分に対する評価も同時に下がっていきます。
イジメられないためにはイジメをする側に回れば良いと考える人もいますが、これは表面上は平和を保てても、潜在的な敵を増やすことになり、いつ自分の立場が悪くなるか分かりません。
保護者との問題は園全体で取り組む
保育士と保護者とのトラブルに関しては、他の同僚や主任、園長などと問題の内容や原因を共有し、一丸となって対処していくことが大切です。
また、もしも自分の失敗が原因の場合、下手に隠したり嘘を吐いたりするのでなく、反省すべき点はきちんと反省して、誠実さを示すことも周囲からの信頼を得るために重要です。
保護者を自分の味方にしてしまう
保護者からのクレームや理不尽な要求といったリスクを減らす最善の方法は、保護者との信頼関係を構築することといえます。
保護者との信頼関係を築くには、何よりも保護者ときちんと対話することが必要です。そのため、保護者とのコミュニケーションを積極的に取っていくことも、保育士にとって大切な仕事の1つといえるでしょう。
人間関係の良い職場へ転職しよう
人間関係が良い職場探しのポイント
職場見学で実際の雰囲気を確かめる
職場見学で園を訪れても、その時はあくまでゲストの立場であり、実態の全てを確かめることはできません。しかし、園内が明らかに汚れていたり、もしかすると同僚になるかも知れない人間に対して横柄な態度を取ったりする園であれば、避けた方が無難です。また、保護者や子どものいない場所で、それぞれの保育士がどんな様子で働いているか確認しておくことも大切です。
チームづくりや役割分担がきちんとなされているかどうか
きちんと保育士がチームを組んで保育に当たっていたり、リーダーやサブリーダーといった役割分担が行われていたりする園では、保育のプロとしての自覚を各人が共有できている可能性が高まります。
実際に働いている保育士から話を聞く
チャンスがあれば園で働いている保育士から話を聞くことも有効です。語られる内容が全て本音とは限りませんが、少なくともいきなり人間関係の悪さや愚痴などを語ってくる保育士がいる園では、転職後のリスクが高いと言わざるを得ません。
また、明らかに保育士の年齢層が偏っている園では、異なる世代の保育士が働きにくい可能性もあります。
その他、SNSやネットの口コミサイトなどで明らかに悪口や低評価が多い施設も要注意です。
求人広告は内容だけでなく募集時期もチェック
常に求人広告を出していたり、ひんぱんに保育士募集を行っていたりする園では、何らかの原因で保育士の離職率が高い可能性があります。加えて、給与や業務内容について詳細に書かれているかどうかも、経営姿勢を見るためのポイントです。
小規模保育で働くのも選択肢のひとつ

人間関係で悩み、他の保育園や保育所へ転職を検討するのであれば、小規模保育がおすすめ。一人当たりが担当する子どもが少ないことから子どもと向き合える環境が整っており、ひとりひとりに手厚く保育ができます。責任の重さは変わりませんが、仕事量が減るので、保育士として心の余裕が生まれ、人間関係にも良い影響をもたらすのではないでしょうか。
今回取材を依頼した株式会社メディフェアは、小規模保育を展開し、子ども達の成長を一番に考えつつ、保育士がやりがいをもって働けるよう職場環境を整えています。
「助け合い」の精神を大切にしているため、人間関係が良く、仕事を分担して残業を発生させないという取り組みにも積極的。企業理念として「人のぬくもりが感じられて、個性に寄り添いながら親御さんのフォローもする」ということを掲げており、人と人とのつながりをとても大切にしています。
メディフェアの小規模保育に努める保育士さんに、本当に人間関係や職場の雰囲気が良いか、伺ってみました。
現役保育士さんにインタビュー>>「私が保育士を辞めたかった理由」
トラブル事例集コラム
同僚間のトラブル
実際にあったトラブルの事例として、こういった事があったようです。副主任からのあたりがきつく、今すぐにでも職場を辞めたいと悩む保育士Kさんの話です。
自分の担当しているクラスの部屋が整理整頓されていなかったことを、副主任に注意されたそう。
でもそれはKさんがたまたま休みだったため、ほかの人が怒られてしまいます。
その人は副主任の言い方がきつかったことが嫌だったとKさんに訴え、Kさんは副主任にその旨を伝えますが、「きつく言ったことは問題じゃない、言い訳ばかりするな」とさらにきつく言われてしまいます。職場の雰囲気も悪くなる始末。
Kさんは注意されたことに関してはきちんと理解し、改善しなければならないとはわかっているのですが、きつく言われたことで傷つく人もいるはずで、そこがどうしても引っ掛かっているようです。
また、副主任がほかのクラスのリーダーとばかり仲良くしており、自分は仲間はずれにされている気がするとのこと。もともと今の年度が終われば辞めて、次の職場もすでに決まってはいるのですが、年度が終わるまで気持ちが持ちそうになく、今すぐにでも辞めたい、と悩んでいます。
認可保育園に勤務している、保育士経験年数5年のAさんの話。
同じ職場で、自分の子ども(0歳児)を土曜日勤務の時に職場に連れてきて、職場の子どもたちと同じように保育をしている同僚がいるそうです。
ちなみに普段はほかの園に通園しているのですが、Aさんの保育園の施設長もこのことは知っており、自分の職場に子どもを連れてくることは承諾しているそう。
通常保育は一園のみの利用となっていて、制度的には認められていないはず。同僚保育士の子どもは、本来なら今通っている保育園以外の園で保育を受けさせてはいけないのではないか、とAさんは内心モヤモヤしています。
施設長は内密に受け入れをしているのでしょう。問題ではあるけれど、承諾しているのはなにせ園のトップにあたる人。
はっきりとおかしいことを「これはおかしいですよ」とは、なかなか言い出しにくい。ですがこれが続く限りAさんは割り切れない気分のまま、仕事をしなくてはならない状況です。
保育士になって1年目のフレッシュなBさんの話
勤務先の1個上のある先生が苦手なので、辞めたいと思っているそう。かといってその先生に仕事のプレッシャーをかけられたり圧力をかけられたりといったことは特になく、何か意地悪や嫌がらせを受けたという訳でもないようです。
性格が合わない、雰囲気的に合わないというのか、とにかく不快感を抱いていて、その先生と同じ勤務時間になったり、同じ部屋にいたりすると何も喋れなくなってしまう状態に。
Bさんは、自分はうつ病ではないけれど、うつ病の振りをして病院に行き、医師に頼んで診断書を出してもらい、それを職場に提出して辞めようかなとまで思いつめてしまっています。
嘘をつくのはいけないことだとわかっていても、このまま我慢を続けることで精神的に負担がかかってしまい、本当に心身が疲れてしまうのも避けたいようです。
保育士という仕事は好きなのでこのまま続けていきたいというやる気はあるものの、職場は辞めたいと日々ジレンマで苦しんでいるそうです。
編集部の見解
ちょっとしたトラブルや疑問に感じたことのはずなのに、はじめは我慢できていたことが何度も続くことで心の負担が積み重なっていき、最終的に「辞めたい」とつながっていますね。
ただ自分一人で抱え込んでしまう、真面目な人がこうして思い詰めてしまう傾向にあるようです。
どうせ辞めるとまで思っているのなら、辞める前にダメ元で、上司に相談してみるのはどうでしょうか。それでも状況が改善されないようであれば、退職を考えるもありかもしれません。
先輩後間のトラブル
保育士2年目のCさんの話です。
職場には何十年も働いている先輩ばかりで、ボス的な存在の先生とそのとりまきが存在しており、その先生に嫌われまいと、みんな必死でご機嫌取りをしているそう。ボスに嫌われると、それが上司であってもたちまち周囲から白い目で見られるのだとか。
Cさんは前年度ボスと同じクラスを受け持っており、それによって距離も縮まったはずなのに、今年度クラスが離れてしまうと、またあたりがきつくなってしまったそうです。
これはもう確実に嫌われている、と感じるほど。最初は頑張れたのに、日に日に辛くなり、人当たりがよかったらうまくいったのかなど、Cさんは自分の人間性にも自信を喪失してしまいます。
仕事の時だけでなくプライベートでも暗くなって友人にも指摘されてしまったり、一人のときも悩むのを止められなかったり、頭がいっぱいで爆発しそうな状態だそう。
本当は辞めてしまいけれど、まだまだ仕事で未熟な立場でありながら、辞めてしまっていいものかと悩んでいます。
保育者5年目のDさんは現在、やんちゃな子の多い、落ち着きにやや欠けるクラスを受け持っています。
そんな状態を見かねたのか、先輩先生がDさんのクラスにヘルプのつもりか、毎日のように入って来るそう。
勝手に進行したり、Dさんに対して細かい指導をしたりするようになり、そして少しずつクラスが落ち着くようになってくると、今度はさらにレベルの高い保育を目指すように、とプレッシャーをかけるまでになってしまいました。
Dさんとしてはこれまで責任を持って一人担任を受け持ってきたのに、横から口うるさく言われ、だんだんと自分の保育に自信をなくすように。
元気のなくなったDさんは、保護者さんからも心配されてしまいます。このままではいけないと、先輩先生に思い切って辛さを伝えたものの、言いくるめられて終わってしまったそう。
自分のクラスなのに、先輩先生が保育に入り続けてくることが嫌でたまらないDさん。保育をすることが怖くなってしまい、辛い日々を送っているそうです。
編集部の見解
CさんもDさんも、逆らえない先輩との人間関係によってのびのびと保育ができていないのが辛いところですね。
Cさんの場合はボスの存在をあまり気にせず、自分がいい仕事をできるよう精進することが大切なような気がします。
Dさんの先輩先生は、保育に真剣に取り組んでいるからこそ何とかしてあげたいと思っているのかもしれませんが、行き過ぎた指導は大きなお世話と言えるでしょう。
あくまでいざというときのフォロー、というスタンスで見守って欲しいものです。
園長とのトラブル
保育士試験を受けながら補助の仕事をしているHさん
勤務している園は、園長、理事長(園長の母親)、主任(園長の姪っ子)、副主任(園長の姪っ子)といった家族経営。副主任のパワハラに悩んでいます。
自分のお気に入りの先生には笑顔で勤務中私用の話もしているのに、気に入らない先生には、あからさまに態度に出し、命令口調でまくしたるそう。Hさんもその1人です。
副主任の方針が合わず、辞めてく先生も多いため、常に人手不足で休憩時間前後に掃除や雑用全般をやるものの、全然追い付かず、常に雑用に追われています。
その間主任・副主任は一切やらず、目を光らせてキツい口調で命令するだけ。何かをするたびにダメ出しをして、事あるごとに子どもたちのいる前にもかかわらず、大声で怒鳴ることもあるようです。園長は見て見ぬふり決め込んでいるそう。
Hさんとしては、辞めるのは簡単だけど補助で正職員の募集はなかなかない上、せっかく子どもたちと信頼関係ができてきたのに、裏切るのは嫌だという思いで、なかなか踏ん切りがつかないという状態になっています。
編集部の見解
家族経営の悪い面が全面にでている園ですね。家族内では諌める人が存在しないため、これからも変わることは難しいと思われます。
これまで何人も辞めているとのことなので、保育士がすぐに辞めていくということが日常茶飯事となっており、園側も保育士は使い捨てといった感覚ではないでしょうか。
こういった環境では発言権がある職員がいません。園側に嫌われると自分の立場まで危うくなることがわかっているため、助けてくれる人を期待することも難しそうです。
保護者間のトラブル
「いじめ」という言葉にひどく反応する保護者さんは意外と多いようです。日々の保育の中で、子ども同士が諍いを起こすのはよくあること。
ですが、「うちの子がいじめられている」と思い込んでしまい、それが大きなトラブルに発展することがあります。
保育士の方はケンカしている様子をきちんと見ているため、いつものこと、成長の一つなどといった捉え方をしますが、保護者さんは一部始終を見ていないため、自分の子どもがケンカして怪我でもしていようものなら、「何故うちの子がいじめられたんですか?」と保育士に詰め寄るケースも。
それだけでなく「うちの子を叩いた子どもの親から謝罪がない」などと、相手の子どもや親御さんに怒りが向けられるとこじれるのは必至です。一度こじれると長引いて、解決するのが難しくなってきます。
大きなトラブルになってしまう前に、保育士の方で、できる限りの手を打つ必要があります。
編集部の見解
ママ友というのは子どもを介して友人になっているため、子どもが原因でこじれると途端に関係性が変わる、不安定なもの。
そのため園で起こったトラブルは、あくまで園の責任であることをはっきり伝え、ママ友同士での諍いを未然に防ぐことが大切です。
また子ども同士のケンカで怪我をした子がいる場合、怪我をさせた側の親御さんに報告するかしないかは、園によって違います。
園全体で対応を同じようにするのが望ましいので、対応の方法などをきちんと園に確認した方が良いでしょう。
保護者と保育士のトラブル
2歳児クラスの保育に入っていたEさんの話です。
ひとりの子どもがなかなか泣き止んでくれなかったので、キャラクターの絵を手の甲にボールペンで描いてあげると、すぐに泣き止んで笑顔を見せて友達の輪に入っていきました。
それを見ていた○○くんが「僕にも描いて!」と寄って来たので、その子の手にも描いてあげました。
するとその日の夜、その男の子の保護者さんから「子どもが『先生が絵を手に勝手に描いた』と言っています」と、電話のクレームが。
Eさんはあれ?と思いながら「○○くんは嫌だったのですね。申し訳ありませんでした」と謝罪します。
保護者さんは「○○には、お友達が嫌がっていることをしてはいけないよ、と言っておきました」と言い、電話を切ったそうです。
2歳の子どもなので、その時々の気分によって言うことがころころ変わる場合もあるとEさんもわかっています。ですがこのようなクレームの電話が来ては、モヤモヤするのは止められません。今後は、子どもが泣いていても描かないと決心したそうです。
編集部の見解
一生懸命保育をしているのにクレームの電話がくると、やはりも納得できませんよね。
保護者さんと関わっていくのは避けられない重要なことですから、保護者さんに好かれる先生になれるのが理想だとは思いますが、保護者さんも保育士やはりも人間。
人間的に合う人、合わない人はいるでしょう。ですが、保育士側にとっては仕事なので、合わないからといって関係の構築を怠ってしまうとますます溝ができてしまい、保護者さんとの信頼関係は成り立ちません。
関連ページ

引用元HP:株式会社メディフェア公式HP(http://medifare.jp/)
メディフェアは、長く働きづらいと思われている保育士の過酷な就業環境を改善するべく、さまざまな面を見直すことで待遇を良くし、保育士の皆さんが楽しく働くことのできる環境を目指しています。
- 年収例:413万円~
- 賞与年2回、月給の3.9~5カ月分支給
- 週休2日制、有給休暇(6ヵ月継続勤務後10日付与)
- 東京都・長崎県を中心に全国各地で保育所を展開