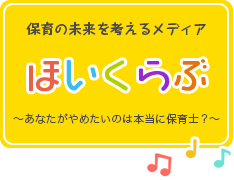- みんなが保育士を辞めたい理由を聞いてみました
- 戻る
- みんなが保育士を辞めたい理由を聞いてみました_TOP
- 保育士として長く働き続けるなら
- 保育士を辞めて後悔したケース
- 保育士を辞めて良かったケース
- 保育補助の仕事を辞めたい
- 保育士になって1ヶ月…もう辞めたい
- 保育士に向いてないから辞めたい
- 保育士の職業病 膀胱炎
- 保育士の職業病 腱鞘炎
- 主任保育士が辞めたいと思う理由
- 新人指導が大変で保育士をやめたい
- 腰痛がひどくて保育士をやめたい
- 音痴が恥ずかしくて保育士をやめたい
- うつ病で保育士をやめたい
- パート勤務の保育士をやめたい
- 保育士の通勤事情
- 制作が苦手で保育士をやめたい
- 加配保育士がきつくてやめたい
- 年度途中で保育士を辞めたい
- 子どもの怪我によるトラブル
- 保護者からのクレームで保育士をやめたい
- 夏休みがなくて保育士をやめたい
- 仕事ができなくて保育士やめたい
- 給料が安い
- 保育士の仕事がとにかく辛いからもう辞めたい
- 人間関係が悪い
- 有休も育休も産休も休めない
- 子どもが多すぎて全体を見れない
- 持ち帰り仕事や残業が多い
- 新卒にも保育士を辞めたい理由を聞いてみました
- 保育士1年目でやめたい
- 保育士2年目でやめたい
- 保育士3年目でやめたい
- 保育観が合わない
- 保育士4年目にやめたい
- 保育士5年目でやめたい
- 保育士6年目でやめたい
- 保育士7年目でやめたい
- 保育士8年目でやめたい
- 保育士9年目でやめたい
- 保育士10年目でやめたい
- 保育士に聞く・福利厚生や待遇のホンネ
- 保育士の転職に必要な基礎知識
- 事業所内保育所はどんな保育所?
- 保育士の資格・経験を活かせるお仕事
- 戻る
- 保育士の資格・経験を活かせるお仕事_TOP
- 保育士から認定こども園への転職
- 保育士から病児保育園への転職
- 保育士から保育ママへの転職
- 保育士からインターナショナルプリスクールへ転職するには?
- 保育士から児童福祉施設(施設保育士)へ転職に何が必要?仕事内容や必要な資格についてチェックしよう
- 保育士から企業内保育施設への転職で必要な資格はある?仕事内容や大変なポイントも解説
- 保育士から居宅訪問型保育への転職に必要な知識や資格は?居宅訪問型保育の特徴も詳しく解説
- 保育士から放課後デイサービスへの転職をするときに必要となる資格は?
- 保育士から託児所へ転職するには?
保育園との違いや大変なポイントも紹介 - 保育士から介護士への転職はできる?
介護福祉士の資格取得は? - 保育士から学童保育士へ転職するには?学童保育士の仕事内容と資格
- 保育士からベビーシッターへの転職に何が必要?仕事内容や苦労も知っておこう!
- ほいくらぶについて
保育士5年目でやめたい
保育士5年目は「中堅」としてさまざまな役割を求められる時期。そのような時にやめたいと思う人はどんな理由を抱えているのでしょうか。
保育士5年目で辞めたい理由は?
保育士5年目の人が仕事をやめたいと思う人は、どんなところに悩みを抱えているのでしょうか。考えられる理由をご紹介していきます。
後輩保育士の指導が思うようにうまくいかない
保育士5年目になると、後輩保育士も多くなってきているはず。そう言った状況になると、必ずと言っていいほど後輩の指導を任されることになります。しかし、誰かを指導するというのは非常に難しいものです。自分が良かれと思って言ったことが異なる意図で受け取られたり、何かを説明してもうまく伝わらなかったりといったことは当然のように起こります。
後輩の指導がはじめての場合は、慣れるまで非常に悩むことになる人が多いようです。
保護者との関係がうまくいかない
担任を持っている子どもたちの保護者との関係がうまくいかない、というものは、どの年次でも抱える悩みと言えるでしょう。ほとんどの保護者とはいい関係を保てていても、中には少しのことでもクレームを入れてきたりする保護者もいることがあります。そんな保護者との関係に悩んでしまうこともあるかもしれません。
同僚保育士との関係に悩んでいる
後輩保育士との関係に悩むと同時に、先輩保育士との関係に悩まされることもあるかもしれません。何年目だったとしても、相性が良くない人というものはいるものです。仕事上だけでもうまく立ち回ることができれば良いのですが、仕事にまで影響が出てくると仕事自体をやめてしまいたいと思ってしまいます。
自分が理想とする保育が実現できない
保育士としての経験を積むにつれて、自分が理想とする保育が見えてくることでしょう。しかし、理想の保育を実現できるとは限りません。先輩保育士や同僚に止められるなどして、フラストレーションが溜まってしまうことも。あまりにも自分の考えていることが実現できないと、この職場は本当に自分に合っているのだろうかと考えてしまいます。
保育士5年目で保育士を辞めたいと悩んでいる方の声
周りの先生方に迷惑をかけたくない
私は保育士として5年目、現在の園で働いて2年目の正職員です。私は昔から思っていることをすぐ口に出してしまうタイプなのですが、そのせいで保護者との間で気まずくなり、担任の先生などにも注意されてしまいました。今では自分が何を言っても迷惑になりそうで、いつの間にか保護者に対してどう接すればいいのかも分からなくなってしまいました。
※参照元:Yahoo!知恵袋(https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12117068382)
子どもを第一に考える保育ができない
5年目の保育士で、今は4歳児の担任を任されています。クラスの中にハンディキャップを抱えていると思われる園児がいるのですが、保護者は事実から目をそらしているようで、園長や主任に相談してもあまり問題に関わりたくない様子です。担任とはいえ、私はあまり子どもの状態についてはっきりと言える立場でなく、他の子とどんどん差がついてしまっている現状を見ているしかできないことが情けなくて、正直とても辛いです。
※参照元:Yahoo!知恵袋(https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1445942904?__ysp=5L%2Bd6IKy5aOr44CANeW5tOebrg%3D%3D)
保育士として何が正しいのか分からなくなった
保育園に勤めている保育士5年目です。私が働いている園は保育をおろそかにしがちで、職員が集まって行う作業へ参加することが優先されるような風潮があります。むしろ、主任から見ると私は子どもにつきっきりなりすぎているように映っているのかも知れません。しかし私は保育士であり担任でもある以上、子どものことを最優先したいと思っています。もう何が正しいことにつながるのか分かりません。
※参照元:Yahoo!知恵袋(https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11222875951?__ysp=5L%2Bd6IKy5aOr44CANeW5tA%3D%3D)
保育士をやめたいけれどお金や生活が不安
保育士5年目です。現在、妊娠しており、来年の春には彼と一緒に引っ越しも考えているので、仕事をやめたいと考えています。ただ、結婚は来年の予定で、それまでに園をやめてしまうと保険証やお金の問題がどうなるのか心配で不安を抱えています。
※参照元:Yahoo!知恵袋(https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14235953324?__ysp=5L%2Bd6IKy5aOr44CANeW5tA%3D%3D)
保護者への対応が精神的に辛い
5年目の保育士として働いています。移動で園が家から遠くなり、帰宅後も疲れているせいで何もする気が起きません。園内の人間関係に不満はないのですが、保護者対応が気を遣うもので、仕事前にはいつも憂鬱になってしまいます。いっそ園をやめようかと悩んでいる状態です。
※参照元:Yahoo!知恵袋(https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10226844070?__ysp=5L%2Bd6IKy5aOr44CANeW5tA%3D%3D)
自分のやめたい理由を明確にする
やめたいと漠然と思っている時には、すぐに行動に移すのではなく、まずは自分がなぜやめたいと思っているのかをはっきりとさせることが大切です。この部分をはっきりさせずに勢いだけでやめてしまった場合、「やっぱりやめなければよかった」と後悔してしまう可能性もあります。
優先順位を明確にする
やめたい理由を明確にすることで、自分の優先順位をはっきりさせることもできます。自分が仕事を大切にしたいのか、そして仕事をする上ではどんなことを大切にしているのかということもわかるはず。その上で落ち着いて、自分は本当にいまの仕事をやめるべきなのかどうかを考えると良いでしょう。
保育士5年目で続けていくことのメリットを考える
そして考えて欲しいのが、保育士として5年目を迎えた今の状況でやめずに保育士を続けた場合、どんなメリットがあるのかということ。かなり保育士としての経験を積んできているわけですから、いまは理想の仕事ができなくてもこれから先は自分がやりたい仕事を実現できる可能性もあります。
その上で、自分が今抱えている悩みは改善可能かを考えてみましょう。時には1年・3年・5年先の先輩や上司がどのように動いているかどうかを見てみましょう。周りに目を向けて視点を変えてみることで、思わぬところに解決方法が隠れている可能性があります。
保育士5年目でやめることのメリットを考える
保育士をやめない場合のメリットを考えると同時に、やめた場合のメリットを考えることも必要です。その上で、やめた場合のメリットの方が大きそうであれば、職場を離れる必要がある、と判断する場合もあるでしょう。
また、ストレスが溜まってしまい心身に影響が出ている場合には、保育士をやめる、もしくは休職するなどしていったん仕事から離れることで体調を回復させられるというメリットがあるかもしれません。
保育士5年目の他の人はどうしている?
保育士をやめたいと思った時、やめずに続けた人の傾向としては、「他の人の意見を仰いだ」というケースが多いようです。特に、周りにいる先輩保育士であれば同じような悩みを抱え、乗り越えてきたというケースも多いはず。そんな時にどのように行動してきたかを知ることによって、今悩んでいることにどのように対応したら良いかということも見えてくるはずです。
ただし、普段から相談できる関係づくりをしておくことが大切です。
保育士5年目で考えておきたいキャリアアップ
保育士の待遇を改善するために、平成25年から「処遇改善制度」という公的制度が開始されています。保育園に在籍する保育士の平均経験(勤続)年数に応じて、給料に加算率が設定され昇給するという仕組みです。また、それに合わせて保育士のキャリアアップにも注目が集まっており、5年目の保育士であれば新しいチャレンジを始めるのに適しているタイミングかも知れません。
保育士として目指せる役職
保育士としての経験年数がおおむね3年以上あり、さらに都道府県など自治体が主催している担当分野の研修を終了している人であれば、職務分野別リーダーや若手リーダーといった、新しい役職へ就くことできるようになります。
職務分野別リーダーや若手リーダーといった役職に就くことで、毎月の賃金に5千円が加算されるなどメリットが得られるため、現在の園はもちろん、転職活動を行う上でも有利な条件で就職できる可能性が高まるでしょう。
キャリアアップ研修を複数修了する
経験年数がおおむね7年以上で、4分野以上の研修を修了していれば、副主任保育士や中核リーダーといったさらに上位の役職へ就くことができます。そのため、5年目の段階から自治体のキャリアアップ研修へ積極的に参加し、時間をかけて準備を始めておくことも賢明な選択です。
また、キャリアアップ研修には食育・アレルギーや障害児保育など、保育士として学んでおきたいテーマが色々と用意されています。
医療保育専門士の資格取得
病院などの医療機関で保育士として1年以上の実務経験を有している保育士は、日本医療保育学会に所属して所定の研修や論文審査などをクリアすることで、医療保育専門士の資格を取得できます。
医療機関での実務経験が必要になりますが、医療現場で重宝される資格であり、中堅保育士のキャリアアップ手段の1つとして魅力的です。
まとめ
保育士5年目の人が、仕事をやめたいと思う理由や、そんな時にはどのように対応したら良いのかを考えてみました。誰でも仕事を続ける上では悩んでしまうもの。しかし、周りの先輩や同僚に相談することによって最適だと思える道が見えてくることもあります。まずは冷静になってなぜやめたいのか、改善できるところはあるのかどうかを考えてみてくださいね。
関連ページ

引用元HP:株式会社メディフェア公式HP(http://medifare.jp/)
メディフェアは、長く働きづらいと思われている保育士の過酷な就業環境を改善するべく、さまざまな面を見直すことで待遇を良くし、保育士の皆さんが楽しく働くことのできる環境を目指しています。
- 年収例:413万円~
- 賞与年2回、月給の3.9~5カ月分支給
- 週休2日制、有給休暇(6ヵ月継続勤務後10日付与)
- 東京都・長崎県を中心に全国各地で保育所を展開