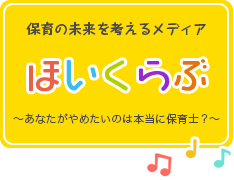- みんなが保育士を辞めたい理由を聞いてみました
- 戻る
- みんなが保育士を辞めたい理由を聞いてみました_TOP
- 保育士として長く働き続けるなら
- 保育士を辞めて後悔したケース
- 保育士を辞めて良かったケース
- 保育補助の仕事を辞めたい
- 保育士になって1ヶ月…もう辞めたい
- 保育士に向いてないから辞めたい
- 保育士の職業病 膀胱炎
- 保育士の職業病 腱鞘炎
- 主任保育士が辞めたいと思う理由
- 新人指導が大変で保育士をやめたい
- 腰痛がひどくて保育士をやめたい
- 音痴が恥ずかしくて保育士をやめたい
- うつ病で保育士をやめたい
- パート勤務の保育士をやめたい
- 保育士の通勤事情
- 制作が苦手で保育士をやめたい
- 加配保育士がきつくてやめたい
- 年度途中で保育士を辞めたい
- 子どもの怪我によるトラブル
- 保護者からのクレームで保育士をやめたい
- 夏休みがなくて保育士をやめたい
- 仕事ができなくて保育士やめたい
- 給料が安い
- 保育士の仕事がとにかく辛いからもう辞めたい
- 人間関係が悪い
- 有休も育休も産休も休めない
- 子どもが多すぎて全体を見れない
- 持ち帰り仕事や残業が多い
- 新卒にも保育士を辞めたい理由を聞いてみました
- 保育士1年目でやめたい
- 保育士2年目でやめたい
- 保育士3年目でやめたい
- 保育観が合わない
- 保育士4年目にやめたい
- 保育士5年目でやめたい
- 保育士6年目でやめたい
- 保育士7年目でやめたい
- 保育士8年目でやめたい
- 保育士9年目でやめたい
- 保育士10年目でやめたい
- 保育士に聞く・福利厚生や待遇のホンネ
- 保育士の転職に必要な基礎知識
- 事業所内保育所はどんな保育所?
- 保育士の資格・経験を活かせるお仕事
- 戻る
- 保育士の資格・経験を活かせるお仕事_TOP
- 保育士から認定こども園への転職
- 保育士から病児保育園への転職
- 保育士から保育ママへの転職
- 保育士からインターナショナルプリスクールへ転職するには?
- 保育士から児童福祉施設(施設保育士)へ転職に何が必要?仕事内容や必要な資格についてチェックしよう
- 保育士から企業内保育施設への転職で必要な資格はある?仕事内容や大変なポイントも解説
- 保育士から居宅訪問型保育への転職に必要な知識や資格は?居宅訪問型保育の特徴も詳しく解説
- 保育士から放課後デイサービスへの転職をするときに必要となる資格は?
- 保育士から託児所へ転職するには?
保育園との違いや大変なポイントも紹介 - 保育士から介護士への転職はできる?
介護福祉士の資格取得は? - 保育士から学童保育士へ転職するには?学童保育士の仕事内容と資格
- 保育士からベビーシッターへの転職に何が必要?仕事内容や苦労も知っておこう!
- ほいくらぶについて
保育士1年目でやめたい
保育士1年目、仕事が辛くて辞めたいと感じている人もいるでしょう。そんな時、どうしたら良いのか考えてみましょう。
保育士1年目で保育士を辞めたいと悩んでいる方の声
上司の顔色をうかがう毎日が辛い
1年目の保育士です。保育園には毎日、吐き気に耐えながら通勤しています。そこまで辛い理由は、上司に当たる先生の顔色をうかがいながら保育業務をしなければならないことと、残業や持ち帰り業務の多さです。残業を断ろうとすると上司が不満そうな顔をするし、子どもたちは可愛いのですが、もう限界です。
※参照元:Yahoo!知恵袋(https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12238154152?__ysp=5L%2Bd6IKy5aOr44CAMeW5tOebrg%3D%3D)
先輩が怖くてモチベーションが上がらない
保育士1年目として、せめて人並みに仕事をできる程度になれればと思い、怖い先輩からの指導にも耐えてきましたが、いつの間にかメンタル的に限界を迎えてしまっていました。今では気が緩むと涙が出てしまって、このままではいけないと思いますが、ほとんど何もできず、不安や焦りばかりが強まっています。
※参照元:Yahoo!知恵袋(https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10238089755?__ysp=5L%2Bd6IKy5aOr44CAMeW5tOebrg%3D%3D)
保育士になったことさえ後悔している
公立の保育園で1年目の保育士をしています。仕事が大変すぎて、毎日を楽しいと思う以上に辛いです。いっそどうしてこの仕事を選んだのかと後悔さえしています。女性の多い環境ならではの雰囲気も窮屈で、先輩保育士や保護者との上手な付き合い方も分かりません。公立保育士の1年目でも辞められた人はいるのでしょうか。
※参照元:Yahoo!知恵袋(https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14227254644?__ysp=5L%2Bd6IKy5aOr44CAMeW5tOebrg%3D%3D)
他の保育士の働き方に納得できない
私は21歳で、公立保育士の1年目として勤務しています。私は、保育士は子どもの気持ちに寄り添える、明るくて優しい職業だと思っていましたが、先輩の先生が子どもに対して厳し過ぎるせいで、見ているだけで辛くなります。また、それを止められない自分にも嫌気がさします。もう保育士として頑張れる気がしません。
※参照元:Yahoo!知恵袋(https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10221224480?__ysp=5L%2Bd6IKy5aOr44CAMeW5tOebrg%3D%3D)
保育士1年目で辞めたい人の割合
保育士として経験の浅い人ほど離職率が高い
厚生労働省が令和2年8月24日に発表した資料「保育士の現状と主な取組」によれば、平成29年時点での保育士の離職率は全体平均で9.3%であり、私立保育園では10.7%と、およそ1割の保育士が辞めていることが示されています。また、経験年数に反比例して保育士の数が減っていき、経験年数8年未満の保育士が全体の過半数を占めることから、長く続けられず離職する保育士が多いことも分かります。
その上、平成27年時点のデータを見ると、経験年数ごとの保育士の数が、2年未満とでは全体の15.5%に対して、2~4年未満になれば13.3%となっており、仮に毎年同程度の人が新卒採用されているとすれば、数年で約2.2%の人が辞めているというデータが示されていました。
この場合、割合でいえば約2.2%はあまり大きくないように思えますが、平成27年時点で保育士として従事していた人の総数は約50万人であり、その2.2%は1万1千人にも上ります。
もちろん、実際は年によって採用数や離職率が異なる上、他にも条件の違いを考えなければなりませんが、それでも多くの人が保育士として勤務したものの、早い段階で離職しているということは間違いなさそうです。
※参照元:厚生労働省|保育の現場・職業の魅力向上検討会(第5回)「保育士の現状と主な取組」(令和2年8月24日)(https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000661531.pdf)
保育士1年目の約74%が就労に不安を感じている
さらに厚労省の同資料によれば、新しく保育士試験に合格した人のうち、全体で約65%、保育関係の就労経験のない人であれば74%が、保育士として働くことに不安を感じていることも示されています。
また、保育業界の経験者であっても約56%が保育士としての就労に不安を抱えており、保育士1年目の人材のケアに保育業界全体で取り組んでいく必要性が示唆されています。
実際、厚生労働省は都道府県や市町村と連携して、保育士の早期離職を予防するために、離職防止につながる研修などを実施していることも重要です。
※参照元:厚生労働省|保育人材の確保(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057741.html)
保育士を辞めた人も勤務状況が改善されれば保育園で働きたい?
厚生労働省が平成29年4月に発表した資料「保育人材確保のための『魅力ある職場づくり』に向けて」では、過去に保育士としての勤務経験があり、現在は保育士として働いていない求職者のうち、再び保育士として働きたくないと考えている人の割合が示されていました。
再び保育士として働きたくないと考える人の割合は、保育士1年目で辞めた人が10%、過去に1年以上~5年未満の保育経験を持つ人で約20%、5年以上~10年未満の保育士経験を持つ人で約30.7%と、以前に保育士として長く働いてきた人ほど、もう保育業界に戻りたくないと考えていることが分かります。
見方を変えれば、保育士1年目で辞めた人の中でも約9割の人は、辞めたくなった理由が改善されれば再び保育士として働く可能性もあるということでした。
※参照元:厚生労働省|「保育人材確保のための『魅力ある職場づくり』に向けて」(平成29年4月)
(https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/library/ishikawa-roudoukyoku/antei/taisaku/joseikin/2904-hoiku.pdf#search='保育人材確保のための『魅力ある職場づくり』に向けて')
保育士1年目で辞めたい理由は?
保育士1年目で辞めたい、と感じる理由はどの辺りにあるのでしょうか。主な理由を挙げてみました。
理想と現実のギャップを感じている
保育士1年目でぶつかる壁として「保育に対する理想と現実とのギャップ」が挙げられます。学生時代は「就職したら子どもたちとこんな風に接したい」と考えながら日々勉学に励んでいたとしても、実際に現場に出てみると状況は異なるもの。そのギャップを感じ、保育士をやめたいと思ってしまうことがあるかもしれません。
保護者とのコミュニケーションの問題
子どもたちを預かっている以上、その子どもたちの保護者との関わりも多くなります。例えば子どもが転んで怪我をした、ほかの子どもと喧嘩をしたなど、保育士側に非がないことで責められたり、無理な依頼を受けたりすることも多くあるでしょう。
周りの職員とのコミュニケーションの問題
保育園は、どうしても女性職員が多い職場です。そのため、女性同士ならではの問題が出てくることも。全ての保育園であるわけではありませんが、職員同士のいじめや嫌がらせなどがないとは限りません。人間関係が悪化すると普段の業務にも支障が出てくるため、保育士としての仕事にも嫌気がさしてくることにも繋がってしまいます。
残業が多い
多くの保育園で残業が発生しているのが現状。保育士の残業を減らすためにノー残業デーなどを設けている園もあるようですが、現実には持ち帰りの仕事が発生しているケースも少なくないようです。持ち帰りの仕事が発生してしまうと、平日だけではなく休日にも仕事をしなければならない状況にも繋がってしまい、プライベートな時間や勉強をする時間などがどんどん減ってしまいます。
給与面で不安がある
どのような職業であれ、1年目は給料が安いことは珍しくありません。しかし、保育士はなかなか収入が上がりにくいというイメージがあり、保育士1年目で必死に働いている中で先輩保育士からそのようなことを伝えられれば、将来に不安を抱いてしまうこともあるでしょう。
教育制度や研修制度が不十分
厚労省の調査によれば、7割以上の新人保育士が実習や研修を必要だと考えていますが、保育園にきちんと保育士を育成できる環境が整っていなければ、1年目の保育士をケアすることもできず、離職率を高めてしまう要因になり得ます。
※参照元:厚生労働省|保育の現場・職業の魅力向上検討会(第5回)「保育士の現状と主な取組」(令和2年8月24日)(https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000661531.pdf)
自分のやめたい理由を明確にする
保育士をやめたい、と思った場合には、まず冷静になってどうしてやめたいのかを考えてみましょう。なぜやめたいのかという理由が明確になれば、自ずと解決方法が見えてくることもありますし、ほかの同僚や先輩もアドバイスしやすくなります。
優先順位を明確にする
「優先順位を明確にする」のも大切なことです。自分の中では何を優先したいのか、例えば自分のプライベートを優先したいのか、それとももう少し頑張ってみたいのかを考えてみましょう。そこで仕事よりも自分のやりたいことを優先したいと思った場合には、転職するというのも一つの方法。
また、もしあまりにも仕事が辛いために体に不調が生じている場合には、体を優先することも考えてみるべきです。
保育士1年目で続けていくことのメリットを考える
ただ、せっかく目標を持って学校で学び、保育士として就職できたのですから、一度保育士として働き続けていくことのメリットも考えてみましょう。
そのためには、「やめたい」と思っている理由の改善が可能なのかを考えてみることが必要です。自分一人で解決できることなのか、それともほかの同僚の力も必要なのかが明らかになりますので、アドバイスを求めることは可能です。
また、目線を変えてみるということも必要なこと。1年、3年、5年先輩など、職場にはたくさんの先輩や上司がいますので、周りを見ることで視点を変えることもできるはず。
このように、1年目の保育士としての悩みを乗り越えることで、今後同じようなことがあったとしても徐々に乗り越えることができるようになるはずです。
保育士1年目でやめることのメリットを考える
逆に、やめたいと感じている理由によっては、いまの職場をやめることで得られるメリットもあるかもしれません。
新しく見つけた職場が今よりも環境が良かったり、着いていきたい先輩や上司が見つかった場合には転職することに意味があったと言えるでしょう。もちろん、入ってみるまで新しい職場はどんなところかわかりませんから、今より状況が好転するとは限らないところが難しいところです。
また、仕事が辛すぎて心身に異常をきたしている場合には、休息をとることによって体調が回復することが考えられるため、やめることによってメリットがあると言えるでしょう。
保育士1年目の他の人はどうしている?
1年目で保育士をやめたい、と思う人は多いようです。人間関係や保護者との関係、現実と理想のギャップは多くの保育士が感じることです。
その中でもやめずに続けた人、実際にやめた人、さまざまなパターンがありますが、やめずに続けた人は、やはり周りに相談できる同僚や先輩、上司がいたことが大きかったようです。逆に自分一人で抱え込んでしまうと、やめる方向にしか頭が働かなくなり、結局やめてしまうという結果に繋がってしまいます。
保育園に限らず、職場というものはチームプレイが大切。ですから、いつでも周りに相談できるよう日ごろからコミュニケーションをとっておくことは大切ですね。
まとめ
保育士1年目の人が、いまの職場をやめたいと思ったときに、いったん立ち止まって考えてみたいことをご紹介しました。仕事をやめたいと思うことは、保育士に限らず多くの人が思うこと。
そこで踏みとどまって続けるか、新しい道へ進むかは自分次第ですが、せっかくこれまでの夢だった保育士になれたのですから、どうしたらやめずに続けていけるのかを一度考えてみてはいかがでしょうか。
関連ページ

引用元HP:株式会社メディフェア公式HP(http://medifare.jp/)
メディフェアは、長く働きづらいと思われている保育士の過酷な就業環境を改善するべく、さまざまな面を見直すことで待遇を良くし、保育士の皆さんが楽しく働くことのできる環境を目指しています。
- 年収例:413万円~
- 賞与年2回、月給の3.9~5カ月分支給
- 週休2日制、有給休暇(6ヵ月継続勤務後10日付与)
- 東京都・長崎県を中心に全国各地で保育所を展開